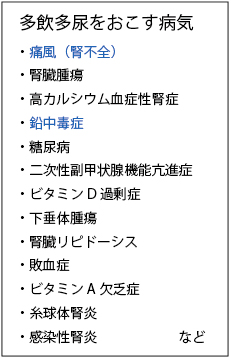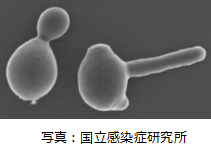変形性関節炎(へんけいせいかんせつえん;osteoporosis)
2015年5月20日 / ☆小鳥の病気
鳥での変形性関節炎は、慢性発情状態のメスや、肥満、高齢の鳥にしばしば発生します。特に肩・膝・足根関節に多く発生します。
原因
慢性発情のメス → 女性ホルモンの影響による骨変化
肥満個体 → 関節への慢性的な負荷
高齢鳥 → 骨関節の老齢性変化
症状
痛みや可動域の制限による諸症状。握力低下によって滑ったり、脚間が広がります。片方の脚の痛みが大きい時は反対の脚に体重をかけたり、患脚を浮かせます。負重のために反対の脚の裏に炎症(足底炎)がおこることがあります。肩関節の可動域が制限されると、飛ぶことができなくなります。
診断
上記の症状に併せて、X線検査で関節領域の骨変形や骨増殖、周囲組織の石灰沈着などが確認できれば、変形性関節炎と診断されます。
治療
変形性関節炎は完治しないため、原因の除去と疼痛管理が中心になります。痛みに対しては、消炎鎮痛剤の内服に併せてレーザー治療や理学療法が効果的です。慢性発情がある場合には発情抑制、肥満がある場合には食事制限による体重コントロールが症状の軽減のために必要です。
©みやぎ小鳥のクリニック
*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。
【参考文献】
・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)
・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)
・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」