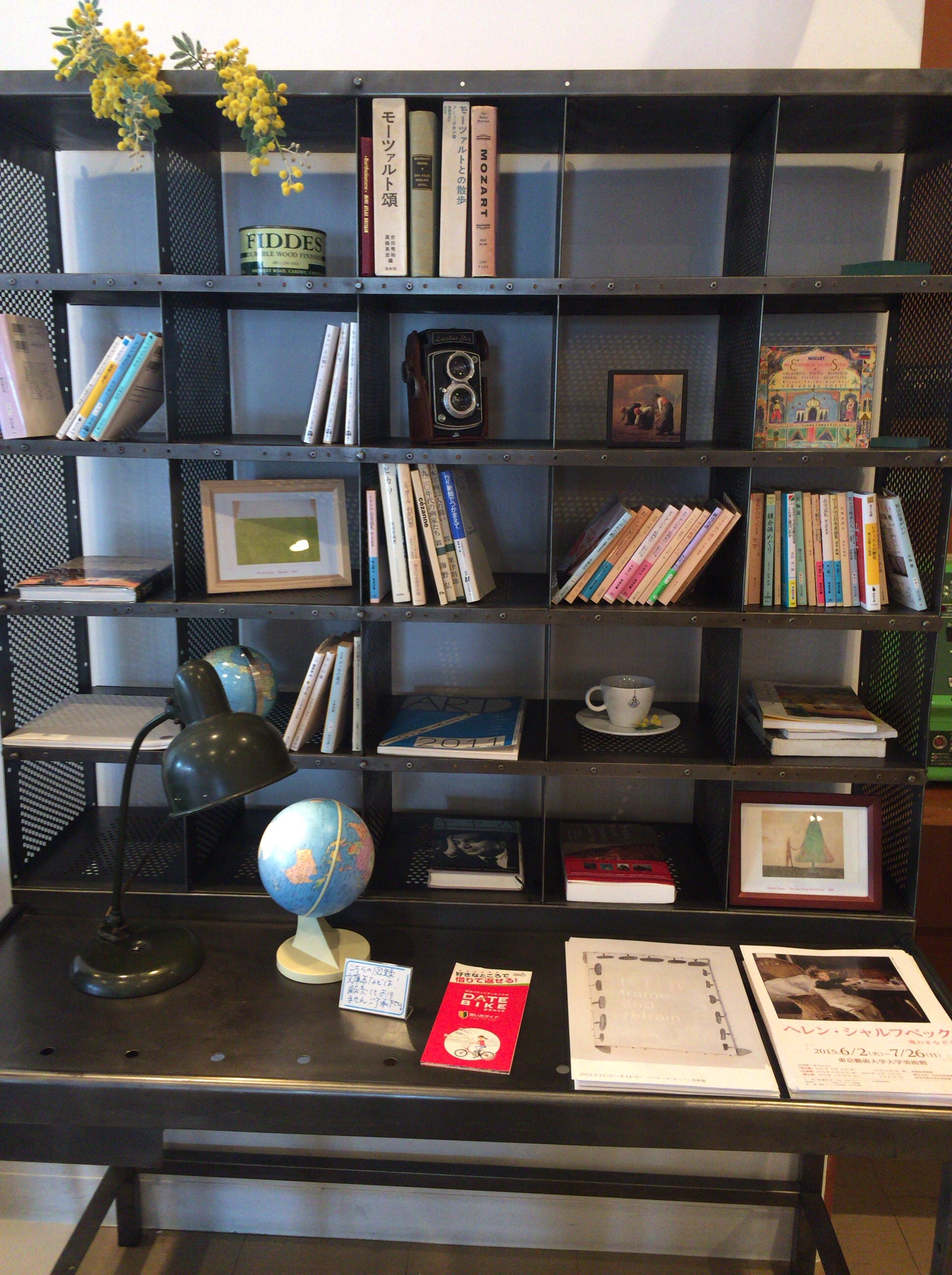超音波検査(ちょうおんぱけんさ:ultrasonography)(エコー検査)
2015年9月10日 / ☆検査

現代西洋医学では、血液検査、X線検査とともに、診断にかかせないのが超音波検査です。
どんな検査なの?
人の耳には聞こえない高周波を使って、内臓を画像としてリアルタイムで確認できる検査です。X線検査が内臓の大きさや形のみの確認であるのに対し、超音波検査は、大きさ、形はもちろん、臓器の内部の状態やX線検査ではわからない小さな腫瘍の確認も可能です。
検査の方法は?
超音波検査装置につながっている端子を鳥の体に直接あてて、体内の様子を観察します。
イメージ画像
なにがわかるの?
肝臓腫大、精巣腫瘍、卵巣腫瘍、卵管嚢胞、卵管蓄卵材症、卵塞症、腹水など主に腫瘍の検出に効果を発揮します。X線検査で卵管がはれていても、なぜはれているかわかりませんが、超音波検査では卵管の内部が観察できるので診断が可能です。また、X線検査では見えない無殻卵も超音波検査では簡単に確認できます。
©みやぎ小鳥のクリニック
*本解説は、下記の参考文献および当院での実績を基に構成・編集したもので す。出典表記のない図、写真はすべて当院オリジナルです。
【参考文献】
・小嶋篤史著「コンパニオンバードの病気百科」(誠文堂新光社)
・海老沢和荘著「実践的な鳥の臨床」NJK2002-2007(ピージェイシー)
・Harrison-Lightfoot著「Clinical Avian Medicine VolumeⅠ-Ⅱ」